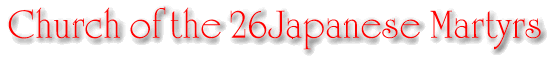|
教会報第266号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
主の降誕と新年のご挨拶
主の降誕のお慶びを申し上げます。
天体の運行に目を向ければ、地球の自転も公転も昨日までと何ら変わることなく、いつも通りに時を刻んでいます。宇宙の大きな流れの中では、一月一日という日は単なる通過点に過ぎないかもしれません。しかし、私たちキリスト者にとって、今日という日は特別な意味を持ちます。それは、この日が「主の降誕から八日目」にあたるからです。教会は、救い主の誕生という大きな喜びを、たった一日ではなく八日間かけて大切に祝い続けてきました。その締めくくりが、この新しい年の始まりと重なるのです。自然のめぐりの中で、ただ時間が過ぎるのを待つのではなく、そこに「神の救いの計画」を見出し、新たな決意で歩み始める。そんな特別な新年の始まりに際し、本年も変わらぬご愛顧と共なる祈りをお願い申し上げます。
聖年の閉幕とこれからの歩み
昨年は「聖年」という特別な一年を過ごしてまいりました。当教会におきましても、教区長の指示に従い、ローマでの閉幕ミサに合わせて聖年の看板(額)を外しました。なお、入口の巡礼スタンプは、聖年指定教会に限ったものではございませんので、しばらくの間はそのまま設置しております。どうぞ引き続きご利用ください。
教皇さまより
二〇二六年元旦、教皇レオ十四世は「世界平和の日」のメッセージの中で、復活した主の挨拶である「あなたがたに平和があるように」という言葉を掲げられました。 教皇様は、軍備拡張や核抑止という「恐怖の支配」に頼るのではなく、相互の信頼と対話による「平和の心」を持つよう呼びかけておられます。たとえ絶望的に見える場所であっても、善の力を信じ、私たち一人ひとりが家庭や地域で「平和の職人」となることが大切です。互いの弱さを認め合い、思いやりの火を灯し続けていきましょう。
教皇庁から神道の皆さまへ
教皇庁には、諸宗教との対話を促進する専門部署があり、毎年元旦には神道の方々へ、春には仏教の方々へメッセージを送っています。 今年、教皇庁は神道の皆さまに対し、武力によらない「武器のない平和」を共に目指そうと呼びかけました。「清らかな心で自然との調和を願う神道の伝統は、平和を求めるキリスト者の希望と深く響き合います。不安や分断が続く現代、宗教者の使命は、人々の心に希望を灯し、地球を守ることです。科学技術が進む今こそ、信仰の知恵を分かち合い、平和な未来を共に築いてまいりましょう」と結ばれています。
東京大司教から
東京大司教、菊地功枢機卿は年頭の司牧書簡の中でかつて日本へ宣教に来られた先人たちに触れ、混迷の続く現代社会を「大海原」に例えられました。私たちもまた、当時の宣教師たちと同じように、希望に向かって歩むよう訴えておられます。 その具体的な歩みとして、世界中で進められている「シノドス的(共に歩む)」な対話を、今後も大切にしていくことが説明されています。文章を拝読すると、私たちへの「宿題」をいただいたような身の引き締まる思いがいたします。本所教会で続けてきた、地区単位での「霊による会話」を通じ、神様のみ旨を共有する感覚を養う歩みは、今後も継続していくことになります。
また組織的な面では、宣教協力体(本所・浅草・上野)について、年内に新たな提案ができるよう準備を進めているとのことです。
枢機卿様は最後に、次のような言葉で結ばれました。 「教会は単に秘跡を受ける機会を提供するだけでなく、信仰を同じくする兄弟姉妹の交わりの共同体であることを意識しましょう。誰かが準備してくれたサービスを受ける『お客様』になるのではなく、一緒になって育てる道に、皆さんの力を貸してください」
|
| |
教会報第265号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年十二ヶ月目」
待ち望む月
十二月のご挨拶を申し上げます
今年の待降節は十一月三十日から始まりますので、主の降誕をしっかりと味わう月となりそうです。そして、通常聖年はこの月で結びの時を迎えます。
「実に、神は独り子をお与えになるほど、この世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びることなく、永遠の命を得るためである」(ヨハネ3・16)(フランシスコ会訳)
この希望の言葉が降誕の祝いの中心となるよう、今から心に留めておきましょう。ベネディクト十六世の最初の回勅『神は愛』は、信仰の中心にあるのが「神は愛である」という根本的な真理であり、この愛こそが私たちの信仰生活の土台であることを教えています。
1.無償の愛
回勅は、人間の愛には「求める愛」と「与える愛」があるとしつつ、神の愛は、見返りを求めない純粋な「無償の愛」であると強調します。 神は惜しみなく愛し、その究極の証として、ご自身の独り子であるイエス・キリストを世に送ってくださいました。クリスマスの出来事、すなわち神が人となって私たちのもとに来てくださったこと、これこそがその明確な現れです。
待降節とは、単に過去の出来事を思い起こすだけの期間ではありません。この神の愛を、今、私たちの「心」の内に受け入れるための、恵みの時なのではないでしょうか。私たちが神を信じるようになるのは、倫理的な選択や高邁な思想からではなく、出来事や人格との交わりから始まります。 教皇様が回勅の序文で指摘されるように、「今や愛はもはや単なる『おきて』ではありません。神は愛のたまものをもってわたしたちを迎えてくださいました。愛とはこのたまものにこたえることなのです」。 神の名が、時には復讐や憎悪、暴力を正当化するために結びつけられることさえある世界にあって、このメッセージは極めて現代的であり、現実的な意味を持っています。
2.愛のわざ、隣人愛の実践
神の愛を心で受け入れた私たちは、その愛を「隣人愛」として実践するよう招かれています。これが回勅の第二の柱です。 項目25ではキリスト者の愛のわざは、単なる慈善活動や感情的な思いやりを超えた、「善いサマリア人のような生き方」でなければならないと語られています。 「善いサマリア人」の模範は、愛が必要な場所において、自分の心を隠さずに開き、その必要に応じて行動する姿を示しています。社会の多様化や高齢化が進み、自分にできることが限られてきたと感じる方もおられるかもしれません。しかし、愛のわざは、体力や財力に限るものではありません。
・困難の中にある友人に、温かい励ましの言葉をかけること。
・日々の生活で、家族や共同体の中での小さな奉仕を喜んで引き受けること。
・そして何よりも、人々のために静かに祈ること。
これら心からの小さな行いの一つひとつが、神の愛を映し出す鏡となり、隣人をキリストへと導く光となるのです。ここで注意すべきは、私たちの愛の奉仕が「無償」でなければならないという点です。ただ、神が私たちを愛してくださったように、惜しみなく与えること。この純粋な動機こそが、私たちの奉仕を真の愛のわざとするのです。
3.愛の共同体として
私たちの共同体は、神の愛を映し出す「愛の共同体」でなければなりません。 クリスマスを迎える準備とは、個人の心の中だけでなく、私たち一人ひとりが神の愛を受け取り、それを隣人へと分かち合うことで、人類共同体全体を愛で満たしていくことなのです。 |
| |
教会報第264号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年十一ヶ月目」
死者の月と
聖書週間の
十一月のご挨拶を申し上げます
今年は、十一月二日の「死者の日」が日曜日と重なります。教区では、三つの霊園で午後二時から、追悼のミサが行われます。菊地枢機卿(カテドラル)小田事務局次長(府中墓地)アンドレア司教(五日市霊園) しかし、皆さまもご存知の通り、最近は熊の出没が心配です。東京都内だけでもこの一か月で三十カ所以上、五日市霊園のあるあきる野市でも目撃情報があります。もし徒歩で移動される方がいらっしゃいましたら、どうか対策をして、十分お気をつけください。
慌ただしかった「昭和百年」
さて、昭和百年とも言われる二〇二五年も、残すところあとわずかとなりました。関西での万博。 国政選挙の結果や、世界情勢の不安。 そして私たちにとって身近なこととして、十二月から健康保険証が廃止になり、生活の上で緊張が続くのではないでしょうか。
教会で過ごした特別な一年・聖年
一方、カトリック教会では、二五年に一度の区切りとなる「通常聖年」を過ごしてきました。この特別な一年、教会の歴史に残る重要な出来事がいくつかありました。フランシスコ教皇の逝去。新しい教皇としてレオ十四世の選出。菊地枢機卿様が、ローマにある枢機卿名義教会へ着座されたこと。慌ただしさはありましたが、これらはすべて聖年にふさわしい、聖霊にみちあふれた大切な出来事に導かれていたと言えるでしょう。新しい教皇レオ十四世は、前教皇様の姿勢を受け継ぎつつも、控えめな印象があると言われます。しかし、そのお言葉は力強く、私たちの心に深く刺さります。
教皇「信仰が揺らぐ時代」の希望
教皇様は、現代社会で信仰が揺らぐ状況について、こう強く述べています。
注1「現代において、キリスト教の信仰が、『弱くあまり賢くない人のための馬鹿げたもの』だと見なされることは少なくありません。つまり、テクノロジーや、お金、成功、権力、快楽のような、他の安定が優先される状況です。(中略)しかし、だからこそ、この場所が、私たちに『福音を伝えること』が求められる場所なのです。」
また、分断が進み、弱い立場の人々を力で押さえつけるような状況に対しては、
注2「あなたがたに平和があるように(略)どこにいたとしてもすべての人に、すべての民族に、すべての地に届きますように。あなたがたに平和があるように。これが復活したキリストの平和です。謙遜で、忍耐強い、武器のない平和、武器を取り除く平和です。この平和は神から来るものです。」
教皇は内外の要人の前で説かれました。
注3「現代、わたしたちは多くの不一致を、また、憎しみと暴力と偏見、違いへの恐れ、地球の資源を搾取し、もっとも貧しい人々を疎外する経済的枠組みによって生じた、多くの傷を目にします。わたしたちは、この練り粉の中で、一致と交わりと兄弟愛の小さなパン種でありたいと思います。わたしたちは謙遜と喜びをもって、世に対してこういいたいと思います。キリストに目を向けてください。」
先月末司祭研修会に参加してきました。現在のメディアに関する内容でしたが、この教皇説教も紹介されました。これからもシノドス的を掲げていくようです。本所教会では地区単位で実践することになります。
「教皇説教」引用箇所
注1 枢機卿団とのミサ
注2 最初の祝福
注3 就任ミサ |
| |
教会報第263号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年十ヶ月目」
ロザリオの月
宣教の月間の
十月のご挨拶を申し上げます
「神無月」の余談と宣教の心
巻頭言を書き始めるにあたり、ふと神学校時代の先輩司祭の冗談を思い出しました。 「十月は『神無月』や『神去月』と言うだろう。だから、もっと神の福音を告げよという『宣教月間』になったんだよ!」と。
もちろん、これは笑い話です。皆様ご存知の通り、この「神無月」という呼び名は、日本古来の信仰に基づき、八百万(やおよろず)が出雲大社に集まって会議をするため、他の土地にはご不在になるという言い伝えに由来しています(これには諸説あります)。 ただ、この「神様が去る」という発想の裏側には、古来、十月が収穫を神に捧げ感謝する「神の月(かむなづき)」であったという説もあります。いずれにせよ、十月が「神」と深く関わる特別な月であったことは確かです。
この日本的な背景を思うとき、私たちは改めて、神様が私たち一人ひとりに託された「福音宣教」の使命について深く考える機会を与えられているように感じます。
「布教」と「福音宣教」の違い
現代において、私たちはしばしば「布教」と「福音宣教(ふくいんせんきょう)」という二つの言葉を使い分けます。この違いを理解することこそ、今、私たちが信仰者として何を大切にすべきかを示唆しています。
一九七五年(昭和五十年)に教皇パウロ六世が発表された使徒的勧告『福音宣教(EVANGELII NUNTIANDI)』は、この精神を現代に強く打ち出しました。
かつて「布教」という言葉は、しばしば教義や制度を一方的に広めること、あるいは信者の数を増やすことに重点が置かれがちでした。もちろん、神の愛を伝える行為に変わりはありませんが、どこか形式的で、受け手の主体性を見失うような印象を伴うこともあったかもしれません。
これに対し、教皇が示す「福音宣教」は、はるかに奥深いものです。
「福音」とは、イエス・キリストを通して示された神様の愛という「良い知らせ」そのものを指します。教皇は、福音宣教とは単に教義を言葉で説くことではなく、教会の存在そのもの、そして信徒一人ひとりの「生き方そのもの」を通して、この「良い知らせ」を世界に「証しする」ことだと説かれました。
その本質を三つの視点に分けて述べます。
⒈「沈黙のあかし」の生き方
言葉で説く以前に、キリストの愛に根ざした奉仕や、見返りを求めない無私の愛を実践する「沈黙のあかし(証し)」が最も大切です。私たちの生き様が、神の愛の最初のメッセージとなります。(『福音宣教』第21節、第41節)
⒉人間性と文化の福音化
福音宣教の対象は、個人の魂だけにとどまりません。人々の生活や文化、社会の構造そのものにキリストの価値観が浸透し、より人間らしい、希望に満ちたものへと変えられていくプロセスこそが福音宣教の目的です。(第18節、第19節、第62節)
⒊内面からの回心と変革
真の宣教とは、まず、宣教する私たち自身が神の愛に深く触れていくことが出発点となります。(第76節)
⒋終わりに
もし「布教」が外に向かって教えを「広める」行為だとするならば、「福音宣教」は、私たち自身の存在と愛の行動をもって神の恵みを「証しする」という、すべての人に及ぶ全人的な営みであると言えるでしょう。(第14節、第24節)
ロザリオを手に祈り、マリア様の信仰に倣うこの月に、私たちの日常生活における一つ一つの行動が、周囲への希望となりますように。 |
| |
教会報第262号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年九ヶ月目」
希望の種をまく「いのち」の月
九月のご挨拶を申し上げます
毎年、9月1日から10月4日までの1ヶ月間、日本の教会は「すべてのいのちを守るための月間」として、特別な祈りと行動の時を過ごします。この月間は、2019年に教皇フランシスコが日本を訪問され、「すべてのいのちを守るため」というテーマを掲げられたことを記念して定められました。今年は、教皇フランシスコが書かれた『ラウダート・シ』(回勅)から10年目にあたり、世界中の教会でも「被造物の季節」として、神さまが造られたすべてのもの、自然や私たち自身との関係を改めて見つめ直す、大切な時となっています。
開催にあたって英和文含めて多くの文書がだされています。それらをみると多くの大切なことを思い起こさせてくれます。
教皇レオ14世は、この「被造物の季節」にあたって、「平和と希望の種」というテーマを選ばれました。イエスさまは、神の国についてお話しされる時、よく「種」のたとえを用いられました。一つの種が地に落ちて死ななければ、たくさんの実を結ぶことができないと教えられました。コンクリートの道端から、小さな花が顔を出すのを見ることがあります。誰が植えたわけでもないのに、たまたまそこに落ちた種が、硬いアスファルトを突き破って咲く姿は、まるで神さまの命の力のようではありませんか。私たち一人ひとりも、キリストにおいて「平和と希望の種」なのです。
この世界では、残念ながら多くの争いや破壊が起きています。それは、人間が自然を自分だけのものとして支配し、利用しようとする「罪」から来ていると指摘しています。自然を壊すことは、最も弱い立場にある人々を苦しめることにつながります。しかし、預言者イザヤは、*「霊が高い天から注がれる」と、希望を語りました。荒れ野が園になり、正義と平和が住まうようになる、と。この「被造物の季節」は、私たちに必要なのは、祈りだけでなく、具体的な行動なのだと強く訴えかけています。
今年の聖年は、旧約聖書にある**「ヨベルの年」に由来しています。「ヨベルの年」は、50年に一度、畑を休ませ、借金を免除し、奴隷を解放する年でした。これは、社会の中で生まれた歪みを正し、本来あるべき姿に戻すための特別な時でした。この世を創造されたのは私たち人間ではなく、神さまです。私たち人間は、神さまの恵みとしてこの世界を与えられた、謙虚な存在であることを思い出す時です。私たちは、神さまと、自然と、そして人間同士の関係を歪めてしまいました。この歪みのしわ寄せは、弱い立場の人々へと向かいます。聖年は、このような歪んだ関係を、神さまが「きわめてよかった」とおっしゃった、もともとの美しい関係へと回復させるため(「エコロジカルな回心」)の時なのです。 この月間を通して、私たちは、神さまが造られたすべての命に心を寄せ、祈り、行動することが求められています。教皇フランシスコは、「私たちは、今成長している子どもたちに、どのような世界を残そうとするのでしょうか?」と問いかけられました。この問いかけは、神さまのもとへ旅立たれた前教皇さまからの、私たちへの最後のメッセージとして心に響きます。被造物を大切にすることは、単なる環境保護ではなく、信仰そのもの、そして人間性に関わることなのです。 今年の「被造物の季節」のテーマは「被造物との平和」です。イザヤ書の言葉にあるように、正義が住むところにこそ、平和と安らかな信頼が生まれます。神さまが定めた、被造界の秩序を尊重することなしには、真の平和を実現することはできません。私たちは、祈りを通して心を変え、日々の生活の中で、小さな行動を積み重ねていくことができます。一つひとつの行いが、この世界の平和につながっていくのです。
すべての命が互いに生かし合う、神さまが望まれた関係へと立ち返るための特別な時です。聖年に合わせてこの月間を過ごすことで、私たちは、神さまと、被造物と、そして隣人との関係を修復し、神さまが造られた世界の本来の美しさを取り戻すことができるでしょう。この「いのち」の月間が、私たちにとって、信仰と人間性の両面から、すべての命を守る生き方を広めていく、祈りと行動の時となることを心から願っています。 どうぞ、この期間、毎日の祈りの中に、神さまが造られたすべての命への感謝と、私たち人間の行いに対する回心を含めてください。そして、小さな愛の行動を実践していきましょう。
脚注 *イザヤ32:15 **レビ25:8 |
| |
教会報第261号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年八ヶ月目」
暑中お見舞い申し上げます
八月は「平和旬間」の月です。終戦記念日である十五日には、ミサの後に教会から一番近い慰霊の場所へ赴き、皆様の思いを乗せて祈りと線香を手向ける予定です。また、九月一日には関東大震災の記念日を迎えます。主任司祭として、谷中墓地にある震災関係者の慰霊碑前でも祈りを捧げたいと考えています。
「平和旬間」は、ご存知の通り、聖ヨハネ・パウロ二世が日本を訪問されたことがきっかけで始まりました。教皇様の平和への力強いメッセージは、今も私たちの心に深く響いています。日本の司教協議会も毎年平和のメッセージを発表しており、今年は特に、戦後八十年という節目の年にあたり、司教団全員の思いが込められたメッセージが発表されました。
この平和メッセージの始まりは、一九八六年九月二六日、当時の白柳大司教が東京で開催されたアジア司教協議会連盟総会ミサでの発言に遡ります。白柳大司教は「私たち日本の司教は、日本人としても、日本の教会の一員としても、日本が第二次世界大戦中にもたらした悲劇について、神とアジア・太平洋地域の兄弟たちにゆるしを願う者であります。(中略)二千万人を越える人々の死に責任をもっています。さらに地域の人々の生活や文化などの上に今も痛々しい傷を残していることを深く反省します」と、日本の教会としての深い反省を表明されました。
以来、原則戦後十年単位の節目と四半世紀単位には、より深く検討された、具体的なメッセージが発信されるようになりました(他年は会長談話)。
戦後50年(1995年):平和への決意
この頃は、戦争が終わって半世紀が経ち、戦争を知らない世代が増えてきていました。司教団は、戦争というものは、神様からいただいた尊い「いのち」を傷つけ、家族を引き裂き、悲しみを広げるものだと強く訴えました。特に、広島と長崎を経験した日本には、核兵器をなくすために声を上げ続ける大きな責任があることを強調しました。また、かつて日本のカトリック教会が戦争に協力してしまったことへの深い反省を表明し、二度と過ちを繰り返さないよう、平和のために尽くす決意を新たにしました。
________________________________________
戦後60年(2005年):非暴力による平和への道
この時代には、世界各地でテロや戦争が起こり、暴力の連鎖が大きな問題になっていました。司教団は、「非暴力」の考え方こそが、平和への道だと語りかけました。日本がこれまで戦争をせず、平和な国として歩んできたことを誇りに思い、この精神を世界に広めていこうと呼びかけました。また、アジアの国々との間で、過去の歴史を真摯に受け止め、心からの「和解」と「連帯」を築くことの大切さも訴えました。貧しい人々と豊かな国との格差や、地球環境の問題も、平和を脅かす大きな原因であるとして、みんなで協力して解決していくことを求めました。
________________________________________
戦後70年(2015年):平和を実現する人は幸い
このメッセージでは、戦争の記憶が遠くなる中で、平和を築くことは「武力によらない平和」を目指すことだと明確にしました。人間のいのちや尊厳が脅かされるようなことには、黙っていてはいけないと強く語りかけています。司教団は、日本が大切にしてきた「戦争をしない」という憲法の考え方を心から支持すると述べました。これは、キリストの教えに基づいていのちを大切にする私たちにとって、当然の願いだからです。また、沖縄に集中する基地の問題や、武力に頼らない話し合いの大切さにも触れ、世界中の争いや貧しさの問題にも目を向けるよう促しました。
________________________________________
戦後75年(2020年):すべてのいのちを守るため
この年は、世界が新型コロナウイルスの流行という見えない脅威に直面していました。司教団は、沖縄戦の悲惨さを深く心に刻み、沖縄の人々が訴える「いのちこそ宝(ヌチドゥ宝)」という考え方に心を寄せました。そして、2019年に日本を訪れた教皇フランシスコの言葉を引用し、「核兵器を持つこと自体が倫理に反する」と強く非難しました。平和は、ただ争いがないだけでなく、「真実と正義を求め、一歩ずつ進む希望の道のり」であり、どんな困難があっても諦めずに進んでいくことだと語りました。
________________________________________
戦後80年(2025年):平和を紡ぐ旅=希望を携えて=
終戦から80年が経ち、戦争を直接知る人がほとんどいなくなった今、戦争の記憶をどうやって次の世代に伝えていくかが、このメッセージの一番大きなテーマです。司教団は、若い人たちが広島、長崎、沖縄を訪れて、戦争の悲惨さを自分の目で見て、心に刻むことが大切だと述べました。
また、司教団は、世界中で軍備を増やす動きが広がっていることに心を痛め、「これは戦争の準備ではないか」と心配する声に耳を傾けています。そして、ノーベル平和賞を受賞した「日本被団協」の活動を称え、核兵器のない世界を強く願う教皇の言葉を改めて引用しました。
最後に、司教団は、平和とは単に争いがない状態ではなく、神様がつくられたすべてのものが尊重され、助け合う「満ち足りた状態」であると教えています。そして、この平和な世界をつくっていく旅を、希望を胸に、みんなで手を取り合って続けていきましょうと、心からの呼びかけをしています。 |
| |
教会報第260号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年七ヶ月目」
七月のご挨拶を申し上げます
今年も半分が過ぎ、残すところあと半年の「聖年」となりました。新しい教皇様のもと、通常の聖年行事も滞りなく進められています。詳細については、バチカンや日本司教団が発信するインターネットニュースサイトをご覧ください。
□聖年と向き合う
映画『パーフェクト・デイズ』に 触れて
厳しい暑さが続いておりますので、冷房を適切に使い、室内で過ごすのが賢明でしょう。聖年にふさわしい映画として推薦されているのが、ヴェンダース監督の『パーフェクト・デイズ』です。映画館での上映はすでに終了していますが、Amazonなどのサイトで視聴できます。渋谷の公共トイレを舞台に描かれたこの人間ドラマは、私にとって創世記の記述を思い起こさせるものでした。スカイツリーも登場し、皆様にも親しみを感じていただけるのではないでしょうか。
□聖座国務長官の来日
先月最後の日曜日、大阪の万博会場でバチカンのナショナルデーが開催されました。ご存知の通り、教皇様は私たちの信仰の指導者であるとともに、世界に向けて重要なメッセージを発信される方です。この式典には、先日開催されたコンクラーベで首席枢機卿に代わって選出を進行されたピエトロ・パロリン枢機卿が来日されました。国務長官という首相に相当する肩書きを持つ枢機卿は、大阪カテドラルでのミサ、東京への移動後のカテドラルでの聖職者の集いミサ、首相との会談、皇族との接見、日本の政治家との意見交換など、多忙な日程をこなされました。
□本所教会「もうすぐ150」企画 今夏もあります!
当教会は、あと4年で創立150周年を迎えます。その機運を盛り上げるべく、昨年から「もうすぐ150」と題し、本所教会にゆかりのある司祭をお招きして主日ミサを司式していただく企画を実施しています。今年は、なんと2人の司祭をお迎えできることになりました。
・中村克徳神父様
8月3日(日)ミサ司式
2005年に叙階された中村神父様は、2001年から4年間、本所教会で司牧実習という形で奉仕してくださいました。現在は大阪高松教区池田教会の主任司祭を務めておられます。『新婚さんいらっしゃ~い』前司会者である桂三枝さん(現・桂文枝さん)が結婚式を挙げられた教会としても知られています。中村神父様は、本所教会での経験が今の司祭職の基礎となっているとおっしゃってくださいます。ミサ後にはささやかな茶話会を設けますので、当時を懐かしみ、今を考える機会となれば幸いです。
・染野治雄神父様
8月10日(日)ミサ司式
染野神父様は現在、御受難会(修道会)の日本管区長という重責を担っておられます。詳細については次号で改めてご紹介しますが、神父様のご心身の健康のため、今からお祈りくださいますようお願い申し上げます。
□聖年のモットー「希望」
聖年推奨映画として指定された『パーフェクト・デイズ』についてパウロ会の司祭は、次のように語っています。「この映画は私個人に語りかけてきた。(中略)身の回りのことに目を向けよう、通り過ぎる時には気づかない人々にも目を向けよう、自分自身にも目を向けよう、自然にも目を向けよう。特に、木々に目を向けよう、木々は、光と闇の相互作用のなかで、影や模様、陰影を作り出す。木々を通して、自分が世界の中でどのような位置にいるのか確認し、目の前にある希望を見いだそう。」
7月という時を有意義に過ごせるよう、心から願っています。 |
| |
教会報第259号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年六ヶ月目」
六月のご挨拶を申し上げます
新しい教皇様が私たちのもとに遣わされました。バチカンニュースの動画の音声を流しながら眠りについたところ、教皇選出を告げる高らかな宣言で目覚めました。午前一時過ぎのことです。
「レオ」を名乗られると聞き、まず八年間同じ現場で働いたレオ一世の霊名を持つ東京教区の故・川原謙三神父様を、次に学生時代からお世話になっているニュージーランド出身のレオ神父様、そして前の池長大阪大司教様を思い出しました。最後に、私の好きな野球チームのイメージまで浮かんできました。教皇様が意図されたレオ十三世が思い浮かばなかったのは、お恥ずかしい限りです。

選出後の週末、紋章が発表されました。神学生時代に「紋章学」という学問分野があることを知りましたが、この度の紋章の日本語解説(中央協議会ウェブサイトにて閲覧可能)からもその奥深さがうかがえます。教皇レオ十四世の紋章では、右下の白い地に本が置かれ、その上に矢で貫かれた燃える心臓が描かれています。これは、アウグスティヌスの『告白』にある「あなたは私たちの心を、愛の矢で貫かれました」という言葉を象徴していると説明されています。
司祭になる前、父からアウグスティヌスの『告白』を贈られました。昔の活字は小さく、紙質も読みやすいとは言えず、内容も平易ではなかったため、せっかちな性格も災いし、残念ながら多くは記憶に残っていません。ただ、父が三カ所に栞を挟んでいたのを覚えています。六月は父の日があり、父が生きていれば百歳を迎える年でもあります。
その栞の箇所を辿ってみましょう。
「あなたは私たちを(あなた)ご自身に向けてお造りになりました。それゆえ、私たちの心はあなたのうちに憩うまで安らぎを得ません。」
(『告白』第一巻一章)
本の冒頭の言葉です。人間の本質的な希求、神への憧憬が力強く表現されていると感じます。真の平安は神のうちにこそ見出せるのだと察せられます。
「古くしかも新しい美よ、わたしがあなたを愛したのはあまりにおそかった。」
(同十巻二十七章)
アウグスティヌスが長年の精神的な遍歴の末、ついに神の愛に気づいた瞬間の喜びと悔恨が吐露されています。「古くしかも新しい美」という対照的な表現は、永遠の神の普遍性と絶えざる新鮮な魅力を捉え、魂が真の美に出会えた感動を伝えています。
「時とは何か。もし誰も私に尋ねなければ、私は知っている。しかし、尋ねる人に説明しようとすれば、私は知らない。」
(同十一巻十四章)
時間についての深い考察です。神の永遠性という観点から見ると、人間が経験する「時間」という概念は容易には解明できません。日常生活で誰もがこのことを認めつつも、その本質に対するアウグスティヌスの思索の深さを感じさせられます。
六月は「み心の月」とされています。イエスのみ心を自ら深く理解しようとすることは容易ではありません。良き導きを得ながら、その理解を深めていければと願います。
|
| |
教会報第258号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年五ヶ月目」
五月のご挨拶を申し上げます
私事になりますが、五月八日は私の叙階日です(まだ日曜日に叙階式が可能だった時代でした)。その日は主の昇天の祝日でした。今年で二十周年となり、本所教会では今月四日にお祝いとなりました。
この場を借りて感謝申し上げます。
通常叙階をお祝いするのは二十五年と五十年すなわち銀祝と金祝そして長寿の時代ですのでダイヤモンド祝やプラチナ祝もみられます。一方で昨今司祭叙階年齢が高くなったため叙階の際にお世話になった方々が病気がちになられているのをみるとささやかな二十年記念感謝の交わりもアリかと私は考えました。今回神学校に入るきっかけを与えて下さった方に本所教会のイースターカードをそえてその旨お伝えしました。
司祭になることを希望していることを最初に口にしたのは教会ではなく通っていた公立の中学でした。通っていた教会の司祭が主任・助任司祭ともに代わり、同時に教会に迫力を感じたのですが、そんな勢いもあって中学二年の課題であった「人生設計」という作文に司祭になることを記したのです。それがどういうわけか学年便りにそのまま掲載され、おまけに町内の掲示板にまで張り出される公開告知となりました。住んでいた区にはカトリック教会は無く、理解されるべきところが誤解されました。映画「エクソシスト」が有名なので、私は西洋版陰陽師になりたがっているという噂まででて、通学路ぞいのたばこ屋さんの人から再考を促されました。
とにかく、あまり目立たない存在であったであろう私が騒ぎの渦中になりました。そんな雰囲気に一番怖い先生といわれた数学担当&担任の先生が「おまえは、なれない」と。そのときの小テストができていなかったのでした。クラス全員の前での一喝という修羅場でありましたが、その全員がその先の私の助け手となってくれました。ですから町の中学校二年A組の仲間たちが私の司祭になりたいという気持ちを応援してくれたのです。自分の弱点を認識し探求しながら無我夢中で生きてこられたのはこの交わりの由縁と思います。
ちょうど五年前、ネットで私を捜して洗礼を志願してきたA組の一人がいました。A組担任の先生のお墓参りに行こうと誘ってくれました。卒業してから知ったのですが、先生はメソジスト派のクリスチャンでした。神学校に入学したことを年賀状でつたえると「すばらしいことです」との返事でした。ですから私のこれまでの司祭職への道は迷惑をかけながらも助けられ関わった人全てが今でも支えであります。
先日その中学課題を見つけました。
三十二歳に司祭になる内容が記されています。実際、私はその年に叙階されています。
三十五歳で主任司祭になると記していました。実際三十五歳で主任司祭に任命されました。
その後教皇さまと同じ祭壇に立つことが叶うとありますが、実際は六年前に実現しました。
使徒座は代替わり。歴史の中で示される神がこれからも聖霊を通していろいろなことが投げかけられるでしょう、教会が皆さんとともに救いの道具となり希望をもちつづけることができますように。
新たな教皇さまに期待しましょう。
ちなみに課題の記録によると私は八十八歳で帰天予定です。それまでどうぞよろしく。
|
| |
教会報第257号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年四ヶ月目」
四月のご挨拶を申し上げます。
四旬節です。祈りと節制の生活がすすめられています。今年の復活祭は四月二十日です。
教皇さまは祈りに感謝している旨のメッセージを伝え退院されました。本所教会の祈り場は終了しましたが、菊地大司教さまは祈りの継続を依頼されています。
日曜日のミサでは観光目的で訪日された方もミサに参加されています。ミサ後に予定をうかがうと、スカイツリーや浅草寺と思いきや、意外にも有名ラーメン店めぐりが挙げられたりします。
先月初旬にいらした旅行者は東京大空襲・戦災資料センターに行くとおっしゃっていました。都営新宿線西大島駅や半蔵門線住吉駅から二十分とのことですが、本所教会の前を走るバスに乗り「東京都現代美術館前」で下車してゆっくり歩くつもりだとおっしゃっていました。
今年は戦後八十年という年になります。イベント関係者から戦災で亡くなった方の芳名読み上げに、本所教会関係の方を加えたいとの申し出をいただきましたが、個人情報の扱いについての観点の違いから実現には至りませんでした。
とはいえ、戦争の記憶を風化させないようにする取り組みも急務になっています。私は両親が戦争体験者なので、普段から「武運長久ミサ」があったこと、千人針、防空壕の話をしっかりききましたが語り部はもう限界です。
今年も台東区の公会堂では写真展示や証言を聞く機会が設定されました。
墨田区の東京都慰霊堂では皇族、知事をはじめ百六十人が参列したと報道されました。このような報道をきくと、東京の爆撃は三月十日のみと勘違いする学習者がいるようですが、実際は爆撃方法の分岐点だったと教わりました。
空襲被害は東京区部が六十回。多摩や島嶼部を含めると百超になります。初回は一九四二年四月の品川と荒川、早稲田中学。四四年は渋谷区あたりに焼夷弾を用いた空襲が始まりました。四五年一月には銀座や有楽町が狙われます。
三月十日は色々情報がありますが、焼夷弾で焼き払う絨毯爆撃、別名「恐怖爆撃」です。春の強風を利用し、また炎上光景を目印にさらに爆撃機が油脂焼夷弾を投下するのです。このときの空襲警報の発動が遅く、川に逃げる多数が衝突し命をおとします。風上に逃げた人には生存者もいたとのことです。都の慰霊堂には引き取り人がいないとの理由で八万柱が安置されています。その後、空襲は山の手、王子、蒲田、多摩へも広がり、八王子大空襲が八月です。
聖年行事に「主にささげる二十四時間」があります。今年は三月二十八日からでした。十年前の特別聖年四旬節教皇メッセージに行うよう明記されていますが、その背景には世界の戦争の傷があります。その傷は今もなお深くなっています。戦争は国と国の政治で起きるのですから参政権を使えば戦争を止めることができるかもしれません。でも「やむを得ない武力行使」と説明されたらどのような立ち位置で私たちは返事をしたらいいのか。そんな迷いや無関心の渦に陥らないように復活祭にむけて整え、希望をあおぐ生き方に姿勢を正しましょう。
|
| |
教会報第256号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年三ヶ月目」
三月のご挨拶を申し上げます
□教皇様のために
教皇様が二月十四日に肺炎のためローマの病院に入院されました。(病室から公務を続けられています。)そこで、全世界に向けて教皇様の回復を祈る呼びかけがなされました。また、菊地枢機卿様も二十五日に東京教区のホームページを通じて教区民に祈りを呼びかけられました。
本所教会では通達前々日に行われた評議会で聖母に祈りをささげました。
バチカンニュースのウェブサイトでは、通常サンピエトロ聖堂の外観をライブ配信していますが、日本時間午前五時と午後八時になると教皇のためにロザリオの祈りが約三十分間配信されます。現地報道によると、広場には二千人が集まり祈りを捧げているとのことです。もしお時間があれば、ぜひアクセスしてみてください。ただし、公式な放送予告ではないため、変更の可能性があります。教皇様ご自身もSNSで祈りに感謝のメッセージを発信されています。
教皇様が入院されているアゴスティーノ・ジェメリ病院は、サンピエトロ大聖堂から七キロ、車で約三十分の場所にあります。病院の前にも人々が集まり、聖ヨハネ・パウロ二世像に向かって祈りをささげています。
□苦しみと信仰
二月十一日を世界病者の日と定めた聖ヨハネ・パウロ二世は、使徒的書簡「サルビフィチ・ドローリス」を特別聖年に発表しました。この書簡は、二度にわたる暗殺未遂事件で心身ともに傷ついた中で書かれたもので、人間の苦しみは普遍的なテーマであり、場所や時を選ばない現実であると述べています。つまり、苦しみは人間の本質的なテーマであり、人間について考えるとき、神との関係なしには理解できないということです。 枢機卿様主司式の殉教者祭を行った本所教会は壮大な殉教者の苦しみに思いを馳せる機会をもっています。特に今年は聖年ですから「司教の日記」「教区ニュース」でも巡礼とからんだ記事が上げられました。
本所教会は幼稚園との関係から巡礼指定教会にはなっていませんが、ブログや教区報で巡礼者が訪れたことが報じられた後、問い合わせが増えています。現状では、巡礼団体ごとの自主的な行動をお願いしています。特に、幼稚園の卒園式の練習期間中は、平日の聖堂内の椅子の配置が変わっているため、制限があります。行事や園児・保護者の往来に関する情報は、お問い合わせいただければお答えできます。
憎悪による焼き討ち、震災、戦災を経験した本所教会にとって、殉教者に保護を求めた歴史そのものが証です。そのため、巡礼を希望される方がいることは理解できます。巡礼は旅であり、巡礼の歩みと自身の人生の歩みを重ね合わせることで、過去の苦しみを振り返ることができます。苦しみの意味を考えることは、人生を考えることと深く結びついているのです。
□四旬節に向けて
三月五日から四旬節が始まります。使徒的書簡と教皇メッセージは、私たちの苦しみがキリストの苦しみに結びつき、人々の贖いと救いに繋がると述べています。このことを意識することで、漠然とした不安が光へと変わる準備になることを願っています。
 |
聖堂横において
教皇フランシスコのために祈る場を
設置しました |
|
| |
教会報第255号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年二ヶ月目」
二月のご挨拶を申し上げます。
『皆さん、ナザレの聖家族の愛の交わりの中で育まれた救い主イエス・キリストの受肉の神秘は、わたしたちにとって、深い喜びと確かな希望のよりどころです。すべての教会との交わりの中で、人となられた みことばと、「救いの錨」である十字架のしるしのうちに、ご自身を現わされる御父の愛を祝うこのとき、わたしたちは東京教区のために、聖年の荘厳な開幕を執り行います。この式は、わたしたちにとって、恵みといつくしみの豊かな体験への序曲です。特にこの戦争と混乱の時代にあって、わたしたちは自らの内にある希望の理由を尋ねる人々に、いつでも答える用意ができています。わたしたちの平和と希望であるキリストが、この恵みと慰めの年の旅をともに歩んでくださいますように。今日、わたしたちのうちに、またわたしたちとともに、このわざを始められた聖霊が、キリスト・イエスの日に完成へと導いてくださいますように。』
聖家族の日の午後カテドラルでこのように大司教様が祈りをささげ、東京教区での2025通常聖年が開幕しました。私はタイミングがあわず、開始時間に遅刻し聖年の扉を開ける式あたりに到着したので、写真撮影しかできませんでしたが、特別な年がきたという意識はもてました。聖年のモットーとなっている『希望は欺かない』(ローマ5・5)は、私たちが希望の巡礼者となって、混とんとした世界各地に希望のメッセージを届ける人となるよう呼びかけています。とくに教皇さまが各所でよびかけられているとおり、慈しみ・ゆるしに満ち、全世界のすべての居場所、そしてともに歩む教会(シノダリティ)の実現のため回心してゆこうという式文です。
先日、「霊における会話」の識別を福音講座でお話しました。別の場で従来用いられた「分かち合い」とどう異なるのかという話がありました。指導する方にもよりますが、私が教わった内容を記します。
「霊における会話が分かち合いとことなる点は互いに傾聴しあうところは同じですが、その中に聖霊の導きを聞き取ることに主眼が置かれています。分かち合いは基本的に結論を出すものではありませんが、霊における会話は饒舌な人も、そうでない人も、押しの強い人も、引っ込み思案の人も、全員が等しく発言の時間を与えられ、そして、そこに聖霊の「声」を識別するのです。そのために話し・聞くこと同様、「祈る」ことが最も重要なことになります。数人のはなし・ステップを終わるごとに「祈る」ことによって聖霊に耳をかたむけることが大切です。こうして単なるききっぱなしや意見調整から合意を得たりするのではなく、意見の相違があっても聖霊がいま私たちをどこへ導こうとしているのかを識別することが大切なのです。
先日中東で捕虜にされ生きて解放された人は希望を捨てなかったそうです。決して欺かれない絶対の信頼と安心感は変わることの多い世界への大きな肯定的な力となるでしょう。
 |
| 扉を開ける式の様子 |
|
| |
教会報第254号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「聖年にあたって」
ご降誕のお祝いと
新年のご挨拶を申し上げます。
本所教会の降誕祭、二十四日の夜は聖堂の補助いすが埋まるほどの人数で祝われました。ミサ十五分前には前庭にあるご生誕の人形にイエス様を据える式を子どもたちと一緒に礼拝し、夜半のミサが始まる流れでした。二十五日の日中のミサでは夜半より多い国外からの旅行者で満たされ、実際のご降誕の場面通り、訪問者を交えての祝いとなりました。国外の方が教会を訪れた場合、三年前の三月発表の東京大司教司牧指針「多国籍の人々がつくる豊かな教会共同体を目指して」もあり、指針をできる範囲で工夫して行っている最中です。国外からの訪問者らしき通りすがりの方が三ツ目通り沿いのマリアさまに敬愛の祈りをささげ、前庭の降誕の人形にかがんで黙想されている姿も見受けられました。
「国外から日本に来られる方は神さまからの贈りものです」と六年前おっしゃった東京大司教は十二月初旬、枢機卿に叙任されました。ネットニュース「バチカンニュース英語サイト」のクリスマスメッセージは菊地枢機卿によるメッセージでした。
教皇様はクリスマスミサを行い、聖年2025がはじまりました。通常聖年というものですので四半世紀ごとの開催となります。日本人の平均寿命は男性八十一歳、女性八十七歳だそうで、そこから計算すると聖年を経験するのは人生で三回ないし四回。大事にしなくてはいけません。免償など信仰者としての振り返りも記載されていますが、今回の勅書にかかれているモットーは「希望は欺かない」というものです。俯瞰してみれば私たちの普段の気持ちはどちらかというと希望は程遠いものです。一番の要因は私たちが神から与えられている『いのちの尊厳』がないがしろにされている現状、戦闘・排除など様々な形でいのちが危機にさらされている闇があります。暗闇が増すほど小さな光が大きく照らされます。教会は「光」となる存在として、たとえ小さくてもすすんで希望の光を放つ存在です。いのちの尊厳をかかげて歩んでいく一年でありますように。
昨年十月に世界の代表者が一同に集まった話合い(シノドズ)が終わり、そこで決めたことを実行するようにと教皇さまは署名されました。さらに実行したことを振り返り、その報告を聖座にするようにとの堅い決意を示されました。その署名された文書の日本語訳が待たれるところですが、本所教会地区単位で先んじて「霊による会話」をはじめているところです。一緒になって祈り、そのうえで語り、これから先をこの識別をもって進んでいくことです。
要ごとの決定は従来のシステム通り主任司祭がすることには変わりないとされていますが、その共同識別からは大きく離れることはないでしょう。
今日、教会内の常識となっている伝統的な考え方は、世間の常識的な考え方として通用しなくなってきています。社会のなかで、わたしたちがどう責任を果たすかを考えなければならない時がきました。そこで、一つの指針となるのがさきほどのシノドス的(ともに歩む)指針です。世界、日本、東京すべてに亘る指針が昨年与えられたのです。
同時期に一年間にもわたって本所教会のこれからを考えてくださった担当の皆さんはコロナ下からの教会の在り方を進めるために「暫定ガイドライン」なるものを評議会に提出されました。カトリック教会の姿は時代とともに光となるので普遍ですが、これから先も道標なき道ではなく希望に向かう年になることは先月からの出来事で証されました。意向通りの一年となりますように。
|
| |
教会報第253号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「孟冬」
十二月のご挨拶を申し上げます
先月は死者の月でしたが、その十三日、多くの作品を世に贈った谷川俊太郎さんが亡くなりました。七十年余りにわたって紡がれてきた谷川さんの作品として、生きるすばらしさを綴った「生きる」。世界中で朝を迎える様子を描いた「朝のリレー」。昭和世代までは教科書にも掲載され親しみをもっていた方もおられるでしょう。他にも絵本「スイミー」、スヌーピーが登場する漫画「ピーナッツ」の翻訳を手掛けられました。アニメ「鉄腕アトム」の主題歌も作られています。やさしいことばで難しいこと・深いことをつたえることができる谷川さんこそが本当のことばの使い手であると俵万智さんは訃報を伝えたテレビのニュースで評しています。
谷川さんが本所教会の設立時母体と同じパリ外国宣教会の一員のマイエ神父様によって設立された幼稚園ご出身だというのを最近知りました。私は、その裏にある教会に通っていました。谷川さんはカトリックメディアであるシグニス制作動画の中で「幼稚園の壁に掛け軸があった。天使が天秤をもっていて青い方に下がったらあなたは地獄。赤い方にさがったら天国にいける。というのを印象深く覚えている」と述べられました。すぐに、対談相手の神父様がきちんと説明してその二元論的な決めつけではないことの誤解をといてくださいましたが、重要な視点だったと感じました。
現在の言葉づかいを考えると、短絡的思考が蔓延している気がします。一つの問題には複数の要因があるのです。教会が「総合的なエコロジー」という言葉を用いているのも私たちに緻密に考えて協同することを促しているように感じます。
谷川さんが十二年前に発表された
「かみさまはいる いない?(あかちゃんから絵本)」では一言での決めつけを避けた総合的な神を探求する視座を感じます。また三十年前には「かみさまへのてがみ」も翻訳されています。こどもからの問いかけの形で神と人のかかわりが表現されていますが、純粋に谷川さんは日本語にされています。これはとても高度なことなのです。
十一月末に司祭研修会があり、この巻頭言の原稿は研修先で執筆しています。枢機卿任命、補佐司教誕生祝いなど司祭団で行い、枢機卿様・補佐司教様からのメッセージをいただき、ハラスメントについて学び、司祭同士で「霊による会話」などを行ったのですが、最終日のミサ説教で「二十年前の司教叙階のときに選んだ「多様性」というモットーについて今はもっと多岐にわたる意味を持っている」というような内容が印象にのこりました。
谷川さんの話にもどります。谷川さんは出身高校の生徒に向けて「あなたに」という詩を贈っています。著作権の関係で転載はできませんので検索してください。三部構成になっているのですが、そこには孤独に生きていかねばならない人間の性(さが)を示しながら愛されている励ましを感じるのです。
待降節がはじまりました。
神がひとり子イエスを私たちに贈ってくださった愛。そして人を生かすことばをもったイエスが幼子として私たちと出会ってくださったことをうれしく感じるためのよい準備となりますように。
|
| |
教会報第252号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「深冷」
11月のご挨拶を申し上げます。
10月も真夏日が続き、今頃になって涼しくなりました。祭服も冬様式になるのは11月からになりました。
11月は死者の月です。
第1日曜日には教区が持っている霊園・納骨堂で午後2時からミサがささげられます。
カテドラルでは菊地枢機卿様、府中墓地ではアンドレア司教様、五日市霊園では浦野神父様(事務局長)が主司式ときいています。当該墓地の区画をお持ちの方には追悼ミサの案内が届いているかと思います。
最近、以前に主任司祭をしていた教会の信徒からの依頼で結婚式の司式をいたしました。挙式場所は偶然ですが私が洗礼を受けた教会です。リハーサルは死者の月。祭壇脇はマリーゴールドでつつまれていました。メキシコの死者の月の習慣だそうです。死者を偲びそして感謝し、生きる喜びを分かち合うことを目的と記されていました。他に飾られていたのは以下の通りです。
パペルピカド
パペルピカドは死者の日を祝う喜びと、紙を巻き上げる風を表しているとのこと。
カラベリタ(どくろ)
カラベラを模した飾りは祭壇のいたるところに置かれ、多くは着色や装飾された砂糖菓子が使われるそうです。教会の中にはありませんでしたが。カラベラは死の表象であり、「メメント・モリ」の精神を生きる者に思い出させるためだそうです。「メメント・モリ」はラテン語です。「死ぬことを覚えていなさい」という意味が直訳にちかいですが。現代では「死を意識することで今を大切に生きることができる」という解釈で用いられることが多いとのこと。
ロウソク
ロウソクの灯は「光」、信仰そして希望を示します。
初めてこの光景を見たとき私はこの違和感にびっくりしましたが、若い新郎新婦はディズニー映画「リメンバー・ミー」になじみがあるのですんなり対応できていました。メキシコで生活している方のウェブページを拝見すると、街中にカラベリタがありました。
死者の月というと墓参と追悼という行事のことを私は思い浮かべますが、メキシコからいらした宣教師の説明をうかがって、今をどう生きるかという意識を強く感じました。これから様々なよびかけが私たちにあるでしょう。しっかり受け止めることができますように。
今年の待降節は12月1日からです。
よい11月を過ごせますように。
| パペルピカド |
カラベリタ(どくろ) |
 |
 |
 |
| 洗礼堂 |
祭壇右 |
朗読台 |
|
| |
教会報第251号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「橙秋」
十月のご挨拶を申し上げます。
秋分の日が過ぎたら急に気温が二十度前半になりました。聖堂前の桜も少し前から落葉しています。これからクリスマスにむけて道路から桜の枝をくぐって聖堂正面がはっきりみえることでしょう。体感ですが夏から急に冬を感じさせる環境です。
七月に司教団文書『「見よ、それはきわめてよかった」総合的なエコロジーへの招き』が発表されました。司教団文書は二〇〇一年に「いのちへのまなざし」を発行していますから、二十三年ぶりのよびかけです。
皆さんはこのタイトルにある「総合的エコロジー」の総合的ということばが気になるのではないでしょうか。教皇さまが以前からこの言葉を用いられるたびに、会議で「総合的に」にあたる表現をどう説明すればよいのかを苦労していると担当の大司教さまは話されていました。このタイトルには「インテグラル」と読み仮名風に文字がそえられています。初読のとき、私はコロナを経験した社会がどのような目線で次の世界をみていくかの視座を与えてくださったと感じました。この文書を読み進んでいくうちに総合的と訳されていることばが導く世界観に至るようです。
タイトルになっている「見よ、それはきわめてよかった」は聖書でつかわれている、天地創造の中で出てくることばです。豊かないのちにあふれている世界、宇宙を眺めながら、喜びにあふれている神さまの心をよみとって聖書にこのことばを載せてくださいました。
キリスト教にとっていのちは与えられた尊い賜物です。それを感謝のうちに受け止め育(はぐく)むことは人間の責任であり、人類に託された大きな使命です。日本のカトリック指導者は司教団です。司教団はこの書をとおして、すべてのいのちを守る取り組みに参加するよう広くよびかけています。
神がつくられた世界のあるべき姿の実現を目標として歩みをすすめていくために、教皇さまの回勅「ラウダート・シ」に学び、神と他者と自然とそして自分との調和ある関係を追及して生きていくための呼びかけです。
日本の教会は一九八一年に聖ヨハネ・パウロ二世教皇が来日されたことを受けて一九八四年に日本の教会の基本方針を発表しました。そしてそれを実現する道を探るために招集された福音宣教推進全国会議の動きを通して日本の社会の中で福音の光が灯され、その光に導かれ一人ひとりの人間としての尊厳が守られるよう働く決意を著しました。
「いのちへのまなざし」は五年前に改訂されています。そして七月発行のこの文書はこのことをよく深めています。今年の秋は短い期間かもしれませんが一読の書にこの二冊を選んではいかがでしょう。
|
| |
教会報第250号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「夏の祈り」
暑中お見舞い申し上げます
いつものことのように感じますが酷暑です。長期間にわたっていますので皆様無理しないように。二十年前よりも平均気温は五度以上ですし、最低気温が真夏日の気温とでています。外に出る時間を考えるレベルです。暑いからせっかちになるのではなく、気持ちをクールに適応してください。
八月は平和旬間です。ご存知のとおり八〇年代に聖ヨハネ・パウロ二世教皇の来日によってこの期間がはじまりました。このとき私は未成年でしたが、記憶にあります。たしか侍者は当時神学生だった幸田司教様でした。その式典に行く途中、新宿と有楽町のあたりの高架下にはうずくまるひとを見かけたものです。駅前では軍歌を大音響で流す車をみました。
傷痍軍人という言葉をご存知でしょうか。戦争によって傷痍を負った兵士のことです。足を引きずりながら決して清潔とはいえない毛布をまとい往来していました。戦中は名誉の負傷とされましたが、ポツダム宣言後恩給が打ち切られその後支援の改善ははじまりましたが、まだ問題があるときいています。
その数日前、今は亡き西川神父様と(当時通っていた教会の司祭でいらっしゃいました)新宿のガード下でうずくまっていた方から手招きされました。神父様と目でどうしようか確認して、二人で近づいたのでした。服装はなんとなくカーキ色でなにかの制服かなとそのとき思いました。くしゃくしゃの紙をニコニコしながら差出してくださり、神父様が広げて見せてくれました。そこには「恩給証書」とあり、そのうえに赤い斜線がされており、消印がおされていました。何を意味しているのかわかりませんでしたが、期待が成就しなかった感じが伝わり、切ない気持ちになって二人無言で歩いたのでした。あのニコニコは証書がもらえたからではなく、足を止めた二人がきたということの表情でしょう。
そんな当時だからこそ、聖ヨハネ・パウロ二世教皇が一生懸命さを感じる日本語で「戦争は人間の仕業です。戦争は死です」とマイクにのって広まったお気持ちは確かに胸をうちました。
この平和アピールから四十三年を経た今年の菊地大司教よる司教協議会長の平和旬間にあたっての談話『無関心はいのちを奪います』の最後の段落に記されています。
『わたしたちは過去の過ちに謙遜に学び、その過ちを繰り返さないように努めることができるはずです。幾たびも目撃してきたいのちに対する暴力を止めることができるのは、わたしたち自身です。』
この数年教区の平和旬間の担い手の委員会は解散され、新しく結成された「カリタス東京」という団体によってアレンジがされています。ですから各教会の持ち回りの企画実行はなくなり楽にはなりました。でも誰かひとりが平和旬間の幟をたてただけでは無関心が広がるスピードが速まるだけです。
今年から本所教会として石原三丁目(新橋行き)バス停裏にある『殉職慰霊碑』に終戦の日、すなわち聖母被昇天のミサ後にそこに赴いて追悼の祈りを行います。教会周辺が焼け野原になったのでたくさん祈りをささげる場所があるのは承知していますが、これから恒久的に聖母被昇天ミサ後に祈りにいくことを評議会で認めてもらいました。
三月十日の東京大空襲があったとき十五歳を最年少とする電話交換手三十一名は「なにがあってもブレスト(送受器)を手放してはならない」という命令をもとに炎の中にて死亡しました。この碑は二度とこのような悲劇の起こらないことを祈願して昭和三十三年に建立されました。教会にいらっしゃる方が利用されるバス停のすぐ裏です。ご一緒に祈れれば幸いです。無関心の反対語は関心をもつことですから。
|
| |
教会報第249号 巻頭言
パウロ 豊島 治 神父 |
「元主任来訪」
七月のご挨拶を申し上げます。
気温・気圧の変化で体調管理が難しくなりました。ご自愛ください。とはいえ、七月にも主日があり、ミサに招かれています。体調を整えて聖堂に集い、賛美と感謝をささげましょう。
六月三十日に築地教会は百五十周年記念ミサ。大司教様司式です。現在の主任司祭はレオ・シューマッカ神父様です。
九月十六日には神田教会の百五十周年記念ミサが行われます。現在の主任司祭は立花神父様です。
さて、五年後には本所教会もこの百五十周年の番がやってきます。意識をもって取り組んでいこうと思います。しかし百五十年は長い歴史です。四半世紀である二十五周年であれば設立創生期の方のお話がきけますが、一世紀半となると何を準備すれば良いかわかりません。本所教会が百五十周年となる二〇二九年に私が主任司祭でいるかもわかりません。ということになると長い時間をかけての準備を必要とする案件の責任が取れません。そこでこれからの四年間、本所教会で過ごした経験のある司祭による主日ミサ司式を企画してみました。原則毎年七月に行なおうかと思います。
今回来てくださるのは加藤英雄神父様です。二〇〇六年にいらして隣にある本所白百合幼稚園の園長を兼務された主任司祭でした。主任司祭と幼稚園長という役務はとても多岐な配慮が必要だったのではないかと拝察します。
カラオケ好き。歌好きというのも健在です。
七月二十一日と二十八日の二回、本所教会の十時ミサに来ていただくことにしました。なぜ二回来ていただくのか、それは加藤神父様に会う機会を多く持つためでもありますが、二十八日は隣の本所白百合幼稚園児のために共同祈願で祈ることになったためです。これは今年教皇さまが宣言された「世界こどもの日」の意向に合わせ日程調整して行われるものです。
どうかこの日だけでなく幼稚園児のために、お祈りください。
私は加藤神父様がかつて司牧しておられた秋津教会に赴任したことがあります(今年加藤神父様は、およそ二十年ぶりに秋津教会に戻り協力司祭をされています)。加藤神父様のファンも多く、教会遠足を加藤神父様のいらした鴨川教会に設定したくらいです。大型バス二台で二時間半かけてきた私たちを高速出口あたりにて自ら出迎え、バスの速さに合わせて走り鴨川教会まで道案内。ミサでは笑顔で「ありがとう。ありがとう。」と呼びかけておられ、それも穏やかな表情でした。バスが退屈でぐずっていたこどもたちもキョトンとしながら静かにミサにあずかっていました。加藤神父様の司式のミサの雰囲気はまたあの時を思い出すこともあるでしょう。
加藤神父様が本所教会にいらっしゃる日は学校の夏休みシーズン。子供や青年のキャンプで不在となる司祭の助っ人として他の教会でミサをささげるため、当日私は加藤神父様と共同司式できませんが、歴史の中で示される神さまのわざが思い起こされるひと時となりますよう願っています。
|